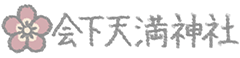時を超えて語り継がれる、神社の由緒

仁和2年 (西暦886年) 香川県の国司に就任していた菅原道真公は、42歳の厄除けの神事と、菅原家の繁栄を祈り、当時の古社でご祈願されました。
また、この地の景勝をことのほか好まれ、えげ郷に4郡 (那珂郡,多度郡,三野郡,豊田郡)を管轄する国府の支庁を置きました。
そばにあった国学の禅宗の学寮でお釈迦様をお祀りすると「顕正院 」と呼ばれるようになり、仁和3年 (西暦887年) から政務と共に 病で苦しむ人々を救われました。

寛平2年 (西暦890年) 任期を満了し別れを惜しまれた道真公は、その翌々年自らの神像を刻まれ家臣にお授けになられます。
道真公が薨去された延喜3年 (西暦903年) 小さな祠を造営し賜りました神像をお祀りしました。
延喜3年創祀より、代々の藩主 (綾氏,藤原氏,生駒氏,山崎氏,京極氏) および故郷の人々の寄進により鎮まり給うお社でございます。
穏やかな毎日が
続きますように
会下天満神社で
ご祈願ください

文化と伝統が息づく
地域の護り神
兼務社
神社は全国に約8万社ありますが、
神職は約2万人と少ないため、1人の神職が複数の神社の役職を兼任することが
一般的になっています。
それぞれの神社に色濃く残る文化や
伝統を、地域の方と共に未来へつないで
いきます。
ここでは、丸亀市中府町・本島町にある
15の神社をご紹介いたします。